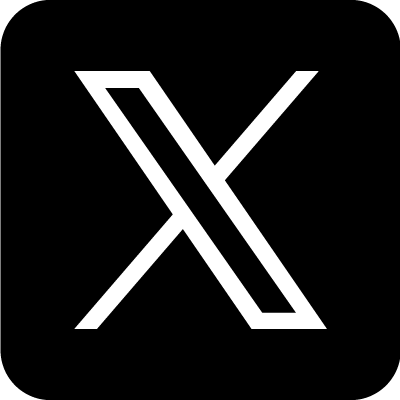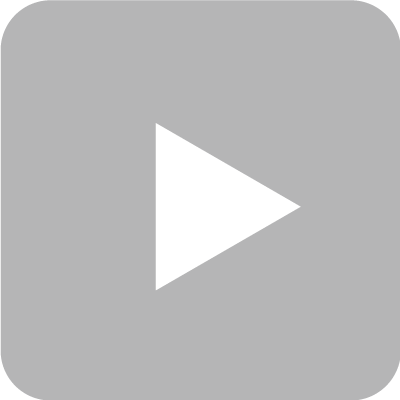横浜市長選 2025 立候補者アンケート
2025年横浜市長選 立候補者6人にアンケート
任期満了に伴う横浜市長選挙が7月20日に告示され、現職と新人合わせて6人が立候補した。投開票は8月3日。
立候補したのは届出順にいずれも無所属で現職の山中竹春氏(52)、前市会議員の高橋徳美(のりみ)氏(56)、元長野県知事の田中康夫氏(69)、元会社員の斉藤直明氏(60)、野菜卸売業会長の小山正武氏(76)、起業家の福山敦士氏(36)の6人。
山中氏は横浜市大の教授などを経て前回選で初当選。「4年間でデータに基づく政策強化と財政健全化を進めた」と主張する。自民、公明の市組織、立民の県組織が「支持」を決めている。
高橋氏は2011年の市議選金沢区選挙区で自民党から出馬して初当選。市長選を前に離党し、6月に市議を辞職した。中学校給食について「一部の学校は自校調理式にすべき」と訴える。
田中氏は長野県知事、参議院議員、衆議院議員を歴任。前回選に続く出馬。「『脱お役所仕事』で市民に尽くす行政を目指す」とし、横浜みどり税の撤廃や中学校給食の自校調理式導入を訴える。
斉藤氏は40年間自動車会社に勤め、定年退職。「ヨコハマ、アゲイン。」をテーマに、港の整備による経済発展や国際園芸博覧会で得た収益を財源にした横浜みどり税の減税などを政策に掲げる。
小山氏は調理師団体や奉仕団体の会長などを務めてきた。「市民ファーストで市民の命を守る」として、小中学校に防災拠点を兼ねる給食室を作ることや市長の退職金ゼロなどを主張する。
福山氏はマーケティング会社などを経営。「子どものために、学ぶ、食べることを行政のサポートで行う」と語り、市立学校でのビジネス教育や自校調理式の中学校給食の段階的導入を訴える。
タウンニュースは、市長選立候補者に最も訴えたい政策や中学校給食、山下ふ頭再開発に対する考え方など、全14問のアンケートを実施した。
立候補者(届出順) 年齢は8月3日(投票日)時点での満年齢
 |
山中 竹春 やまなか たけはる 52歳 |
無所属 | 現 |
 |
高橋 徳美 たかはし のりみ 56歳 |
無所属 | 新 |
 |
田中 康夫 たなか やすお 69歳 |
無所属 | 新 |
 |
斉藤 直明 さいとう なおあき 60歳 |
無所属 | 新 |
 |
小山 正武 こやま まさたけ 76歳 |
無所属 | 新 |
 |
福山 敦士 ふくやま あつし 36歳 |
無所属 | 新 |
アンケート回答
 山中 |
【評価できる施策】子育て支援策の充実 中学3年生までのこどもの医療費の無償化、出産費用の独自助成(最大9万円助成)、妊婦検診額の助成拡大(5万円)、オムツ等の持参をなくす「にもつ軽がる保育園」の開始、総合子育て応援アプリ「パマトコ」のリリース、中学校全員給食の令和8年度からの開始決定など、子育て支援策の充実に取り組んできました。 【評価できない施策】特にありません。 |
 高橋 |
【評価できる施策】小児医療費助成の拡大 【評価できない施策】すべて |
 田中 |
【評価できる施策】見当たらない 【評価できない施策】「山下ふ頭再開発検討委員会」の設置と運営 |
 斉藤 |
【評価できる施策】小児医療費の無償化 【評価できない施策】選挙公約で掲げた「3つのゼロ」が果たされていないばかりか、その進捗の検証すら取り組んでいない。 |
 小山 |
【評価できる施策】IRを取りやめるとして、事実取りやめた点 【評価できない施策】市政全般 |
 福山 |
【評価できる施策】子育て世帯への臨時給付金支給 【評価できない施策】経済政策 |
 山中 |
これまでの4年間でデータに基づく政策強化と財政の健全化をすすめ、子育て支援の充実により子育て世代の転入超過が過去20年で最大となり、誘致した企業による直近3年の投資資本額は2,662億円まで増加し、観光入込客数・観光消費額も過去最高を更新するなど、未来につながる好循環がはじまっています。今後はこれらの好循環をさらに高め、持続的な成長・発展につなげることで、市民生活の安全・安心を確保します。 |
 高橋 |
横浜市政を真に市民の皆様のための市政に転換させることです。市民の皆様は様々な困難を抱えておられ、それを最も熟知しているのは最前線で働く職員たちです。私は彼らが把握している課題を1つ1つ解決することを基本に、職員とともに市民ファーストの市政を実現します。 |
 田中 |
不透明な横浜みどり税を即時撤廃。自校調理方式の学校給食導入。「連結決算」導入で川崎市民と同等の税負担感を早期実現。 |
 斉藤 |
物価高に苦しむ市民生活を鑑みて、時限的に市民税・みどり税の減税を目指す。 |
 小山 |
中学校給食の自校方式での全校実施をはじめとする子育て支援・小中学校の体育館を再整備し拠点とする防災対策・市内のことは市内で循環させる経済政策の「3つの政策」と、市長退職金ゼロ・敬老パス負担ゼロ・みどり税廃止の「3つのゼロ」の実現。 |
 福山 |
経済政策です。横浜市は、5年後に500億円、足りなくなります。以前から、明らかだったこの問題、未解決のまま今に至ります。お金がなければ、助けられない人がいます。あらゆる課題解決において、財源が必要です。ムダを「けずる」こと、財源を「増やす」ことを掲げます。癒着によるムダな支出を削り、横浜の眠ったアセットを徹底活用します。しがらみのない民間出身の私が、若い力と柔軟な発想力で、未来を切り拓きます。 |
 山中 |
市民の要望が最も高いのが大地震、豪雨などの防災対策です。そのため、新たに策定した「地震防災戦略」により、災害対応力の強化、避難所環境の改善を強力にすすめ、発災時も避難生活も、地震に強いまちに。更に災害に強いインフラを整備するとともに、精緻なシミュレーションを活用して浸水リスクを評価し、リスクの高い地区から整備をすすめることで風水害に強いまちに。これらにより、横浜を「もっと災害に強いまち」にします。 |
 高橋 |
まずは、市長のために働く意識から、市民のために働く意識へ転換することが必要です。そのため、市民の皆様のためにどれだけ働いたかを、評価の根本に据え、人事評価制度を抜本的に見直します。 |
 田中 |
公正性と透明性が欠落した市政運営を抜本的に刷新。その意識改革の第一歩として、①市長・副市長・局長・区長・部長・課長が直接市民の願いに電話対応する市政24時間目安箱「#8045」開設。②閉ざされた野毛山の市長公舎と32階建市役所最上階を市民活動の空間として全面開放。 |
 斉藤 |
高度成長期に莫大な人口増加をした本市であるが、その人口ボーナス期から人口オーナス期に転換した今、社会保障費用の負担は増すばかりである。その解決には経済成長を果たし生産年齢人口を増やしていく必要がある。もう一度、東アジアの核となる国際都市になるよう、港湾や商業事業の発展、スポーツ・文化の促進、更にはふるさと納税の減収を『オール横浜』で抑え売上向上に寄与、経済を刺激し税収増の政策を進める必要がある。 |
 小山 |
税収に占める法人市民税の割合が低すぎる。市内企業を育て、市内経済を市内で循環させ、横浜を元気にする必要がある。公共工事の市内企業への発注の徹底などで市内企業を元気にし、経済を成長させていく必要がある。 |
 福山 |
経済政策としがらみの断絶。5年後、500億円足りなくなります。横浜市の財政は危機に瀕しています。この問題は5年前から明らかでした。問題を先送りし、将来世代に負担を強いるか。ムダを「けずる」こと、財源を「増やす」ことを掲げます(詳細はHPにて)。生み出した財源は、こどもへの投資を優先的に行います。「学ぶ、食べる、遊ぶ」機会を取り戻します。政党ではなく市民と向き合い、市民のための市政を取り戻します。 |
 山中 |
横浜市は、これまで、国の臨時交付金を活用して、小・中学校給食費の物価高騰による値上げ分を市が負担する取り組みや、光熱費の削減に寄与するエコ家電の購入支援など、生活に直結する支援に取り組みました。今後も、臨時交付金を活用して、機動的に物価高騰対策に取り組み、市民の家計負担の軽減を図ります。 |
 高橋 |
「宿泊税」の導入と観光・MICE都市として取組みの強化により、宿泊客の増加並びに宿泊税の増収に繋げ、力強い横浜経済の活性化を目指します。プレミアム付き商品券の実施など家計を守る物価高騰等の経済対策を実施します。商店街をはじめとする中小・小規模事業者の皆様への継続的な支援策を構築します。 |
 田中 |
過去の公共事業の起債(借金)償還に充当され、ちっとも緑化が進まぬ、市民一人900円の「横浜みどり税」を即時撤廃。大企業に市民の血税を垂れ流す時代錯誤な「企業立地促進条例」を即時撤廃。 |
 斉藤 |
先ずは自治体にできる減税によって市民の手取りを増やす。時限的に市民税・みどり税の減税に取り組む。現在政府が取り組んでいる「給付金」は自治体の事務負担が大きいことから、国に対しても「給付から減税」への転換を求める。 |
 小山 |
子育て世代には中学校給食の自校方式の実現や様々な支援により義務教育終了までの負担をゼロとする、敬老パス自己負担額をゼロとする、などの市民への直接的支援策と同時に、入札制度の抜本的な改革により経済を市内で循環させることで横浜の経済を活性化させ、物価上昇を上回る経済成長とする。 |
 福山 |
最も必要なのは「生活の土台」を支える直接的な支援です。私はまず、水道代などの公共料金について、夏の間だけでも基本料金をゼロにするなど、時限的な補助を行います。第1子からの保育料完全無料化を実現し、子育て世帯の負担を軽減します。高齢者向けには買い物支援や医療・介護の自己負担軽減を、単身世帯には家賃補助や住宅手当の拡充を検討します。誰もが安心して暮らせる横浜をめざし、支援をきめ細かく届けていきます。 |
 山中 |
米国関税措置の影響を受ける中小企業の資金繰り支援を強化したように、企業を取り巻く環境に応じて、臨機応変に資金繰り支援を行うこと、また、人材不足に対応したデジタル化・省力化への支援など、中小企業が抱える課題に的確に対応した施策を実施することが重要だと考えています。 |
 高橋 |
横浜市の99%以上を占める中小企業の皆様の声をお伺いし、そのニーズに応じて、経営基盤の強化と経営の革新を支援していきます。また、商店街は地域経済の根幹であり、市民の皆様の身近な買い物の場をしっかりとお支えします。 |
 田中 |
原材料高騰に緊急対応する「繋ぎ融資」。中小企業に的確な助言を行う相談体制の確立。人手不足を解消すべく、高齢者3人に1人が独居の政令指定都市YOKOHAMA版「シニア専用ハローワーク」を設置。 |
 斉藤 |
日産をはじめとした本市に工場を持つ大企業が苦境にあえぐ中、そのサプライチェーンを守るために、例えば市がそうした企業の製品購入に対し独自の補助金をサポートするなど、できる限り中小企業を応援していきたい。また中小企業経営者が高齢化する中で、事業継承を地元の金融機関などと連携して、後継者の育成や事業継承を支援する。そして横浜の中小企業でしかできない「オンリーワン製品」を創る施策を行政が支援します。 |
 小山 |
入札制度の抜本的な改革により経済を市内で循環させることや商店街振興策を切れ目なく実行していくことで横浜の企業を後押ししていく。従業員の処遇改善も後押しするなど、経営者の経験と感覚を活かして直接的・間接的支援を行うことで横浜経済を元気にしていく。 |
 福山 |
同じく中小企業経営者として、採用と営業に困っております。即戦力となる人材は東京に集中し、採用難が続いています。経済対策は以下を検討しています。 |
 山中 |
子育て支援策の充実等により、子育て世代を呼び込み、転入超過は過去20年で最大となりました。データに基づく市政運営をすすめ、進出企業は投資を増やし、観光入込客数・観光消費額も過去最高となっています。引き続き、世界水準のグローバル都市をめざすとともに、地域交通施策の充実等による移動しやすいまちづくりを進め、都市の魅力と暮らしやすさを高めることで、未来につながる好循環が生まれると考えています。 |
 高橋 |
人口減少だけでなく、高齢化時代になり、税収が減少し、社会保障や施設の維持管理にも負担が生じ、さらに、気候危機や地政学的リスクが高まる中、 日本最大の基礎自治体として、日本の課題に積極果敢に挑戦する必要があります。 |
 田中 |
45年前の1980年に処女作『なんとなく、クリスタル』で「超少子・超高齢社会」に直面する現在の日本を予言していた作者として、他地域から住民を奪い取る現在の絵空事な「横浜移住アピール行政計画」を撤回。人が人のお世話をして初めて成り立つ「福祉・教育・医療」の充実で実質経済成長率5%を最終年度に達成した長野県知事時代の経験を活かし、377万人の住民が今後も住み続けたい街へと再生。 |
 斉藤 |
市は50年後、統計上で二割の人口減少。労働生産人口の減少は深刻で税収の確保は大きな課題。先ずは近隣の川崎や東京と比較し劣った子育て支援政策を充実、子育て世帯が[住みたいまち横浜]を前進させます。また人口減のカバーには国際都市横浜の原点に立ち戻り、排他的な観点ではなく外国人の方々と[共生]できる社会を築ける語学や生活習慣の教育への取組み、ルールやモラルが守られる環境整備で真の国際都市を実現します。 |
 小山 |
東京の一極集中など、国の施策によるところも大きいが、横浜のポテンシャルを活かし、中学校給食の自校方式での実施などの子育て支援や防災拠点の整備、経済活性化により横浜を活力あるまちとし、現役世代に選ばれるまちとすることで人口減少を食い止め、人口400万人を目指す。 |
 福山 |
「選ばれる都市」を目指すこと。市民税依存の財政は、今後更なる危機に陥ります。税収の減少・労働力不足・地域経済の縮小・インフラ維持困難といった複合的な課題を引き起こします。以下対策案です。 |
 山中 |
令和3年12月からこれまで、市民の意見を丁寧にお聞きし、山下ふ頭再開発検討委員会での検討、答申を経て、市として「基本的方向」を公表しました。テーマの第一に「世界に誇れる、魅せる『緑と海辺』空間」を掲げた、山下ふ頭の将来像をもとに、市民意見をいただきながら、事業計画を策定し、令和12年頃の供用開始をめざします。 |
 高橋 |
山下ふ頭は港湾都市横浜を支えてきたふ頭であり、今後も横浜経済活性化の拠点となる重要なエリアである。従って、再開発の方向性については、専門家や地元関係者、市民、事業者の皆様など、できるだけ多くの意見を取り入れて決定することが重要だと考えます。市民の皆様の意見が割れるような状況になった場合には、住民投票も検討します。 |
 田中 |
大谷翔平選手の通訳が収監された「スポーツベッティング(スマートフォン使用のスポーツ賭博)」の本拠地とする計画を全廃し、利権の巣窟だった山下ふ頭を市民の憩いの場として"ハマっ子の森"に大改造。高層ビルが建ち並ぶ一方で緑化が遅れた「みなとみらい21」地区の「ヒートアイランド」現象を軽減する。 |
 斉藤 |
山下ふ頭を『市民・事業者・港湾関係者』三方良しとなるような、ハーバーリゾートが歴史と未来が交錯する開発に取り組みます。 |
 小山 |
防災対策の観点から現状の形状を維持し、有事の際は物流の拠点としてすぐに活用できる状態とする。平時は現状の暫定利用を恒久化し、四季折々・その時々のタイムリーなイベントを行う会場とすることで、賑わいと人の流れを創出する拠点とする。 |
 福山 |
横浜の"顔"として市民に開かれた場所にしたいです。30年後の横浜市民が誇りに思えるような「環境」「経済」「文化」を調和させた再開発を進めたいと考えます。たとえばブルーカーボン生態系の再生と連動した海辺のエコパーク、国内外のスタートアップが集うビジネス拠点、横浜の歴史と芸術を体感できる文化施設などです。山下公園・中華街とも一体化し、市民にも観光客にも愛される"横浜らしさ"あふれる空間を実現します。 |
 山中 |
共働き家庭が増加する中で、全員喫食の中学校給食を早期に実施するため準備を進めてきました。約1万人の生徒によるメニューコンクールや、市内の名店シェフ監修によるメニューなどにより、新しい給食に対する期待感が高まっています。温かい汁物の食缶による新しい給食の保護者を対象とした試食会では、回答者の92%から良い評価を受けています。今後も、生徒や市民の皆様とともに、新しい中学校給食をつくっていきます。 |
 高橋 |
ハマ弁を進化させ、川崎市でも実施している安全で温かく、そして美味しく食する事の出来る食缶方式を採用し、子供達が笑顔になる新たなYOKOHAMAスマイル給食にチャレンジ、横浜市の中学校給食は、自校方式や配送方式など地域ごとに柔軟に対応する。その為に必要な追加予算や、小学校の給食室の早急な冷房設置の予算を確保します。 |
 田中 |
冷たくて不味くて子どもたちから悪評紛々なデリバリー方式を全面撤回。自校調理方式の学校給食を導入。災害の際に避難所となる学校で地域住民に温かい食事を提供可能な都市ガス・LPガス併用の給食室を整備。「食べることは生きること」の基本理念の下に全ての小中学校に栄養士・栄養教諭を配置し塩分控え目の天然出汁の給食実現で残菜率が2%台に減少した足立区に代表される真っ当な給食を実現。 |
 斉藤 |
大阪市のように順次「親子」や「自校」方式を順次導入し、スペース的に難しい北部・東部などの地域には給食センターを設置、あらゆる角度から「温かくて美味しい」中学校給食の実現に取り組みます。 |
 小山 |
デリバリー方式は冷たいおかずや容器の衛生面など多くの課題がある。防災対策として整備する体育館に調理施設を併設することで自校調理方式での中学校給食の全校実施を進める。横浜において中学校給食は過去2回の市長選でも争点となっており、全校自校方式で進めなければ将来にわたって同じ議論の繰り返しとなる。 |
 福山 |
中学校での全員給食の実施は大切な一歩です。ただし、温かく栄養バランスの取れた食事を提供するためには、デリバリー方式では限界があります。私は大阪市の現場を視察し、親子方式で温かく栄養バランスの取れた給食が実現されているのを確認しました。横浜でも段階的に自校調理または親子方式へ移行し、子どもたちが楽しみにできる「食」の時間をつくります。健全な身体を育てる、食育の面でも意義ある取り組みです。 |
 山中 |
旧上瀬谷地区は、基地返還まで長年にわたり土地利用が制限されてきており、この地で開催されるGREENxEXPOやその後の土地利用には地元の熱い期待が込められています。今後、周辺道路の整備や、開催の周知を強化することはもとより、開催により、気候変動や環境との共生についての理解を深め、GREENxEXPOのレガシーとして、環境にやさしい活動への参加や、緑に親しむ豊かな暮らしにつなげていきます。 |
 高橋 |
花博を一過性のお祭りではなく、脱炭素や郊外部の活性化などを加速させる花博にすることが必須。指摘されている課題の機運醸成については、市内各商店街で花博を周知するための取組みを行い、開催中には屋外で来場者自身が日頃の活動を披露するなど参加型のイベントなどを検討します。会場費については、協会や国と透明性のある議論をするとともに、交通渋滞対策として車線の拡幅や交差点の高架化などを着実に進めます。 |
 田中 |
開催費用の3分の1を横浜市が負担し、半年間で入場者1000万人を想定する「横浜花博」は、世界第3位のテーマパーク「ユニバーサル・スタジオ・ジャパンUSJ」ですら半年間に800万人なのに実現不可能な計画。長野県知事就任の前後に関与した「愛知万博(愛・地球博)」の成功と教訓を活かし、抜本的で具体的な見直しプランを国・県に提案し大改造する。 |
 斉藤 |
過去の万博も様々な問題を抱えてまいりましたが、始まれば運用の改善に取り組み、良い結果を残すことも過去にはあり、開催準備が進む中、安易に大きな計画変更は更に混乱を招くことになると感じます。現状変更可能な問題に取組み、園芸博覧会成功に向け市民の絶大な協力を呼び掛けることを続けることが不可欠です。 |
 小山 |
市民の皆様に対しての花博への理解を得る取り組みが不足している。市独自の事業ではなく既に予算の執行もされていることから、花博自体は成功を期すべきであるが、市の財政的負担のさらなる増には慎重にも慎重であるべきと考える。会場へのアクセスにはLRTの導入など大胆な発想で望む必要がある。 |
 福山 |
「世界を迎える博覧会」から、「市民が誇れる未来資産」へ。 |
 山中 |
都心臨海部では、世界に誇れる水際線の形成や山下ふ頭の再開発、新たな都心臨海部のみどりの創出をすすめ、郊外部では、上瀬谷地区でGREEN EXPO後の成長拠点として、ジャパンコンテンツを発信する新たな観光・集客の拠点や、農業を身近に感じるまちづくり、公園では環境活動の拠点づくりをすすめます。この2つの拠点が連動・成長するまちづくりをすすめることで、もっと「成長・発展」を続けるまちにします。 |
 高橋 |
観光客数を増加させる事は横浜経済の活性化のために重要な施策であり、国や民間企業と連携しながら大規模国際会議の誘致など観光、MICEの取組みを強化します。また、宿泊税を導入し、財源の確保に繋げます。 |
 田中 |
377万人の地域住民が誇りを抱ける福祉・教育・医療の充実で横浜の魅力を再構築してこそ、急がば回れで横浜への観光客のみならず移住者を増やす。この基本理念の下に、イヴェント開催で横浜市外の企業に血税を垂れ流し、雇用創出も経済効果も産み出せず、日帰り客が9割を占める現在の観光行政を抜本的に見直す。 |
 斉藤 |
市が更なる国際都市を目指すならば、世界的人気キャラクターとタイアップも必要と思います。スポーツでは横浜マラソンを「走ってみたい」と思う世界のランナーが増えるような、ベイブリッジをコースに含むなど、魅力ある世界の8大マラソンに育成してまいります。 |
 小山 |
港湾都市・横浜の魅力を感じていただける現在の取組を更に進める他、インナーハーバー地区の回遊性の向上のための新交通の導入など斬新な発想でまちづくりを進めていく。公民連携・官民共創をマッチさせやすい分野であり、柔軟な発想で公共スペースを稼ぐ空間に仕立て、市民にも還元していく。 |
 福山 |
"日帰りのまち"から"滞在のまち"へ 横浜はすでに「来てもらえる街」です。これからは「泊まりたくなる街」へと進化する必要があります。日帰り観光客と宿泊観光客では、一人あたりの消費額に2倍以上の差があります。以下、施策例です。 |
 山中 |
カーボンニュートラルの実現に向け、市民、事業者の行動変容、脱炭素イノベーション、市役所の率先行動が大切です。家庭向け省エネ・再エネ設備の導入支援、分別・リサイクルの推進、中小企業の脱炭素化に向けた設備投資への支援、公共施設のLED化の推進や次世代自動車への転換などを進めます。これらの取組に加え、今後はグリーン社会の実現に向け、サーキュラーエコノミーを推進し、地球にやさしい循環型都市をめざします。 |
 高橋 |
温室効果ガス実質排出ゼロを目指すためには、再生可能エネルギーを確保することと排出量の削減が重要です。そのため、川崎市など近隣自治体と連携した水素・アンモニア資源の供給、企業の皆様の脱炭素化の推進、市民の皆様のさらなる脱炭素化の取組など、本市全体の横断的な対策が必要と考えます。 |
 田中 |
長野県知事時代に地元業者と共同開発し、鋼鉄製と同じ強度を国土交通省が認定した間伐材を用いた「木製ガードレール」を市内全域に敷設。きめ細かい「維持修繕」を地元企業が担う「地域密着型公共事業」を入札改革で推進し、地域の雇用を増進する。 |
 斉藤 |
市の2050年排出ガスゼロへの取り組みは、各分野で広がりを見せておりますが、コストやインフラが伴わない、一部は、誤った環境対策と感じます。特に電気自動車の普及には、住宅事情など様々な問題も多く、その有効性をに見極めた政策が必要です。 |
 小山 |
公共交通の最新型車両や技術の積極的な導入、新交通の整備、住宅の不燃化支援に断熱効果を求めるなどでCO2削減を図っていく。 |
 福山 |
上記の実現は、未来の世代への責任であり、都市の競争力の根幹です。この目標を単なるスローガンにせず、"暮らしの質の向上"と一体化させて推進します。温室効果ガス実質ゼロに向け、再エネ導入の加速に加え、ブルーカーボン生態系(アマモ場など)の再生とクレジット化を進めます。公共施設の省エネ改修やEVインフラ整備、市民・企業と連携した"見える化"による行動変容を促し、都市全体で脱炭素のモデルをつくります。 |
 山中 |
特別市は、市と県の二重行政によるムダを解消し、市域内の行政サービスを一元的に担うことで、利便性の向上と効果的な施策展開をめざす制度です。それにより、生活に密着した行政サービスを向上させ、地域の実情を踏まえた課題解決や、強靭で安全・安心なまちづくりをすすめることができると考えています。しかし、現在、市民が「特別市」を選択するための法制度はないため、まずは、「特別市」の法制度化をめざしています。 |
 高橋 |
賛成。人口減少時代に、特別市制度と同時に道州制のあり方を検討し、地方自治体同士が競争し合うのではなく、共栄していく新たな地方創生のあり方を検討する必要があると考えます。 |
 田中 |
神奈川県を弱体化する「特別市」構想に反対。全国20政令指定都市では県道の維持管理を始めとして既に道府県から移管された事業が大半。警察本部・県立高校・県立病院・県立音楽堂・県管理の河川を除いて全ての地方行政は横浜市が担当。政策本位・カネの掛からぬ政治を掲げ四半世紀前に導入「小選挙区制」が現在の政治の劣化を生み出した苦い教訓を活かし、「かたち」の変更でなく「あり方」の意識改革が必要。 |
 斉藤 |
「特別市」の課題は多いですが賛成です。神奈川県との関係性を検証すると横浜市民は負担と行政サービスの還元において非常にバリューが悪い、横浜市も決して楽な財政ではないため近隣の川崎市とタッグを組んで特別市への移行を進めていくべきだ。 |
 小山 |
賛成。二重行政の解消は行財政改革を進めるうえで重要であり、権限・財源の移譲もすすめるべき、現状の政令市では制度上の限界を迎えている。 |
 福山 |
私は賛成です。税財源と権限を市に一元化することで、地域の実情に応じた柔軟な行政運営が可能になります。市民生活を守る現場がより迅速に動ける体制をつくることに他なりません。一方で、警察署など広域的な機能について「広域インフラ・治安維持機能」をどう担保するかは、極めて重要な懸念事項です。神奈川県と連携し、分担・補完体制を明確に整備します。二重行政の解消と市民サービスの質向上を両立させます。 |
 山中 |
地域と連携した実効性ある対策と自助・共助・公助による備えが大切です。公助としては、データを活用した浸水対策、また、地震対策では学校体育館エアコンの整備、学校・公園トイレの洋式化、備蓄の質と量の拡充、災害時の物流や上下水道を確保するインフラの強靭化、耐震基準を満たしていない住宅への支援拡充、地震火災対策の充実、そして災害時に他都市からの応援を受けることを想定した広域防災拠点の整備に取り組んでいます。 |
 高橋 |
臨海部や木造密集地域での地積調査を実施し、地積調査率を50%まで引き上げるとともに、狭あい道路やがけ地防災対策や地域の要の消防団の充実など、防災対策を充実強化し、自助・共助の取組みを進めます。 |
 田中 |
市民を護る消防・救急の司令塔を海抜1mの本庁舎に移転。横浜市の経営戦略を担う市役所分室を海抜70mの上瀬谷地区に設置。避難所となる市内の500校近い小中学校に備蓄品を整備。定年55歳「退職自衛官」を「学校と地域を護る」職員に積極採用。 |
 斉藤 |
先ずは迫りくる天災に備え、「減災」と「防災」また、地域の「共助」についての市民への啓もう活動を進めます。そして関東大震災の被害によって生まれた山下公園などを通して、改めて災害の恐ろしさやその対策の必要性を伝えていきたい。 |
 小山 |
小中学校の体育館を強固な建物に再整備し、防災拠点とする。日常から市民食堂・こども食堂などの地域コミュニティ拠点として活用し、足を運んでもらう機会をつくることで、有事の際の避難の意識付けにもつなげていく。 |
 福山 |
「命を守るインフラ整備」が最も重要だと考えます。横浜市は人口の規模に対して防災施設が不足しており、避難所の機能強化や防災トイレの配備も足りていません。早急に対策が必要です。高齢者や障がい者など要配慮者を取り残さない体制づくりも欠かせません。災害時には、AIやアプリを活用した情報共有と、地域の見守りなどアナログの力を組み合わせることが効果的です。市民・企業・行政が一体となって命を守るまちを築きます。 |
 山中 |
市長として、18区をすべて回っていますが、商店街のにぎわい、緑豊かな公園や農地の風景、動物園で楽しむ親子の姿、歴史的な街並みや港の風景、それぞれが横浜のイメージを形づくる景色として、やすらぎや、憩い、活力を感じる、多彩な魅力のある街だと実感しています。 |
 高橋 |
金沢区です。歴史や文化、工業団地、大学、八景島、動物園、仏閣も多く、お祭りも盛んで、横浜で唯一観光協会もあります。 |
 田中 |
4年前の横浜市長選挙時の回答と同じく、昭和12年(1937年)に建設された「ねぎ坊主」の愛称で親しまれる蔦(つた)の絡まる高さ26mの鶴見区馬場の鶴見配水塔。アジアを中心に十数カ国の人々が団地建設時から暮らす人々と共存共栄する泉区上飯田町の神奈川県営いちょう団地。 |
 斉藤 |
野毛山公園展望台 |
 小山 |
中央卸売市場。育てていただいた場でもあるが、海からの日の出など景色もきれい。 |
 福山 |
港の見える丘公園です。僕自身は青葉区で育ちましたが、幼少期、毎年、元旦の初日の出を港の見える丘公園に、見にいったことを覚えています。両親の初デートの場所が山下公園であり、新婚時、山手町に住んでいたからです。家計の問題で、両親が離婚するときも、最後に両親と共に、港の見える丘公園に行き、最後の別れをしました。僕にとって、特別な場所です。 |
関連記事
2025横浜市長選 検証・山中市政の4年〈上〉 敬老パス無料化、模索中2025横浜市長選 検証・山中市政の4年〈中〉 データを用いた政策運営
2025横浜市長選 検証・山中市政の4年〈下〉 子育て施策に注力
参議院選横浜市長選 高校生が投票立会人に
横浜市長選 元会社員の斉藤直明氏が出馬表明
横浜市長選 自民市連が現職・山中氏の支持決定
横浜市長選 告示日の選挙運動制限に立候補予定者から不満の声
横浜市長選 立候補予定者説明会に10陣営
参院選と横浜市長選のポスター掲示板設置進む
参院選市長選 貴重な機会 大切に
横浜市長選 会社経営の福山敦士氏が出馬表明
横浜市長選 山中竹春氏が再選出馬表明
横浜市長選 自民が独自候補擁立を断念へ
山中市長、再選出馬は「適切な時期に判断」
山中市長、再選出馬報道を認める
横浜市長選 元長野県知事の田中康夫氏が出馬へ
山中市長 再選出馬報道を否定
横浜市長選立候補表明の高橋徳美市議が自民会派離団
横浜市長選 7月20日告示、8月3日投開票
横浜市長選 市議の高橋徳美氏が出馬へ
今夏の横浜市長選 つま正・小山会長出馬へ
2021年 横浜市長選挙 特集